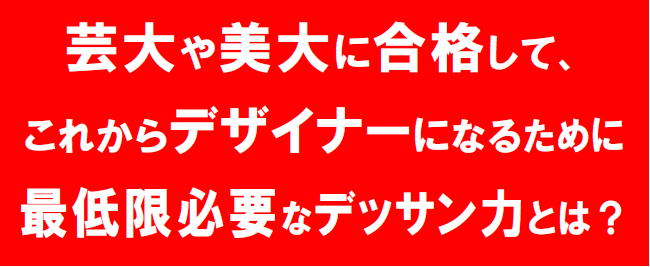

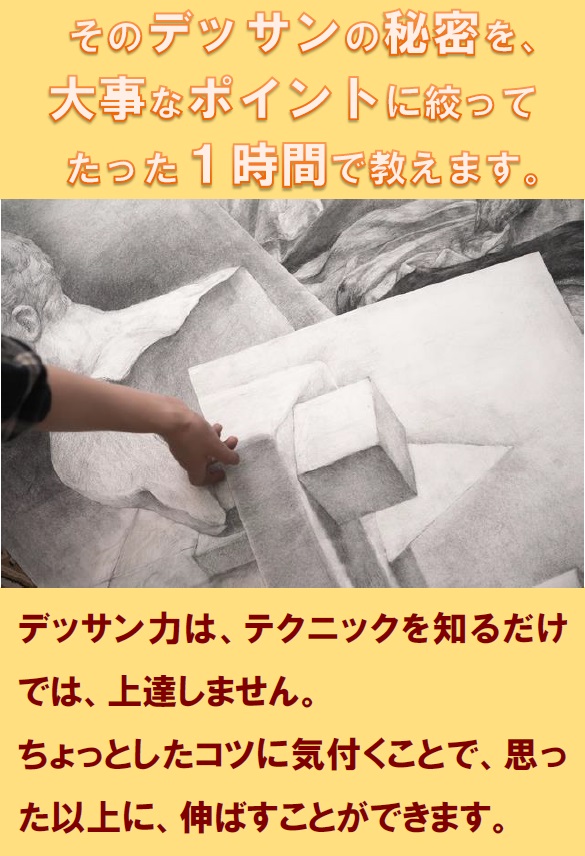
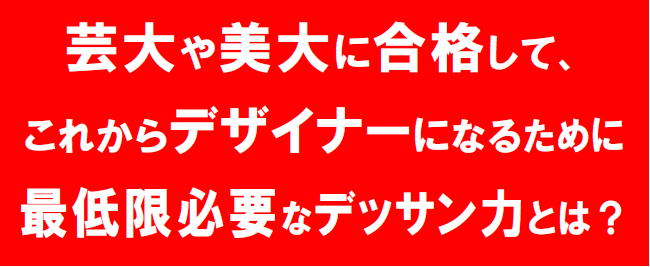

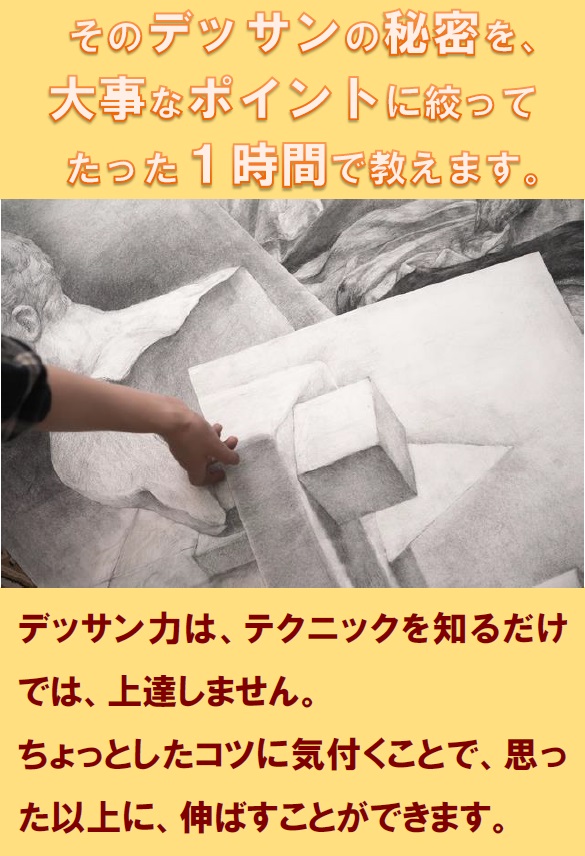
「デザイナーになりたい」
「デザインを学びたい」
そんな希望を持っている人の有効な手段が、美大のデザイン専攻で学ぶことです。
しかし、入学するためには試験があり、そこで重要なのがデッサンです。
デッサンは実技ですから、自分で手を動かし、描けるようにならなければいけません。
そのために、さまざまなテクニックを学び、吸収する必要があります。
しかし、美大の受験日は、刻々と近づいてきます。
それまで、普通に、デッサンの技法書を読んだり、美術の先生の指導を聞いているだけで、間に合いますか?
先輩が描いたデッサンや、デッサンの本に掲載されている参考作品を見てみると、簡単そうに見えたので、自分でもデッサンをしてみました。
しかし、なかなか、うまく描くことができません。
同じように描いているつもりなのに、なぜ、上手にデッサンすることができないんだ?
そこで、いろいろなデッサンの参考書を読んで、描いてみたのですが、やっぱり、うまくいかない。
だんだんと、手が疲れてくるし、目の前の画用紙は、修正を繰り返して、だんだんと黒くなっていく。
受験は、どんどんと近づき、時間がなくなってきます。
他にも、やらなくてはいけないことがあるのに、ちっともデッサンが上達しない。
だんだんとイライラしてくると同時に、どうしていいのか、わからなくなりました。
答えが見つからないので、不安になるし、同じところを、グルグル回っているみたいでした。
やっぱり、デザイナーになるのは難しく、無理なのかな、と、あきらめそうになりました。

しかし、そんな私が、あるきっかけで、デッサン技術が上達し、無事、希望の美大に合格することができました。
そして、卒業後は、念願のデザインの仕事につくことができたのです。
では、その「きっかけ」とは、なんだったのか?
それは、手に入る限りの、ありとあらゆるデッサンの技法書を読み、実践したことです。
街の本屋や、図書館にある本だけではありません。
古書店にも行き、過去に発行された、優秀なデッサン本も何冊も、参考にしました。
そこには、デザインを学ぶ学生に特化されたデッサンの技法書もありました。
それらを読みこなし、実践するには、多くの時間がかかりましたが、3月におこなわれた追加入試で、なんとか、ギリギリで、見事にデザイン専攻に、合格することができたのです。
この時の体験から、自分が役立ったデッサン本を、
『デザイン古書専門アルダス書店』https://aldus.ocnk.net/
というネット古書店で紹介しています。
しかし、いくつものデッサン技法書に描かれたポイントを必要な部分をまとめ、整理することで、もっと効率よく、デッサンを習得できるのでは、と、思いついたのです。
そして完成したのが、デッサンを学ぶための特別レポート『デザインのためのデッサン講座(考え方・初級編)』です。
この特別なレポートでは、デザインを学ぶために必要なデッサンについて、わかりやすく解説しています。
そして、単に、手を動かすためのテクニックではなく、どのように考えて、デッサンを描けばいいのか、という根本的な、基礎の基礎について、丁寧にお話ししています。
これらのヒントを読むだけでも、デッサンに行き詰っている人は、なんらかのヒントを見つけることができるはずです。

●PDFデータ、全体123ページ
イントロダクション:デッサンは、考え方が重要(全22ページ)
第1章:デザインのためのデッサン講座をはじめます
第2章:なぜ、デッサンは、難しく感じるのか?
第3章:今回のデッサン講座の狙い
第4章:本講座の全体の構成と、その内容の紹介
第5章:今回のデッサン講座で、目指すもの
第1部:デッサンの必要性とは何か?(全16ページ)
第1章:自分にとって必要なデッサン技術を見極める
第2章:デザインに、デッサンが必要なのは、なぜか?
第3章:写真があるのに、なぜデッサンを学ぶのか?
第4章:デザインのためのデッサンとは何か?
第2部:デッサンをおこなう前の考え方(全15ページ)
第1章:デッサンは、「線」の使い方が重要です
第2章:鉛筆デッサンにおける影の描き方
第3章:デッサンを上達するために必要な4つの要素
第3部:デッサンの実技に、すぐに使える考え方(全21ページ)
第1章:デザインのためのデッサンに必要な遠近法
第2章:デッサンは難しい、と感じたら、基本形体を描こう
第3章:デッサンを描く順番について
第4章:デッサンを上手に描くために、鉛筆の使い方をマスターする
第5章:デッサンは、イーゼルを使って描こう
第4部:デッサンのためのトピックス(全21ページ)
第1章:デッサンを、楽しく、おもしろく学ぶために
第2章:デッサンを上達するコツは、良いデッサンを、たくさん見ること
第3章:デッサン技術を向上させる近道
第4章:デッサン上達のための場所を、いかに確保するか
第5章:デッサンの第一歩は、身近なものを描くこと
第5部:デッサンを実践するために大切なこと(全28ページ)
第1章:デッサンは、全体をとらえ、バランスよく描く
第2章:デッサンで、立体感を出すポイント
第3章:最初は、シンブルな物からデッサンをしよう
第4章:デッサン上達ために、とても大事なこと
第5章:デッサン上達のために、制限時間を設定する
第6章:デッサンを、きちんと評価するには、客観的に見ること
おわりに
※ページ数が多いように感じますが、わかりやすい文章で書かれているため、スラスラと読み進めることができます。
60分もあれば、読み終えることができるでしょう。
どのようなものか、読んでみたいと興味を持ってくれた方のために、無料のお試し版を、ご準備いたしました。
最初の「イントロダクション」(全22ページ)を読んでいただけます。
こちらで、今回の特別レポートの全体像をご紹介しています。
ぜひ、読んでみて下さい。

今回、ご紹介している『デザインのためのデッサン講座(考え方・初級編)』ですが、私の知識と経験を、十分に盛り込んだため、読んでいただければ、デッサン上達へのヒントを知ることができます。
しかし、ポイントを効率よくまとめ、短時間で習得できるといっても、やはり、早く始めれば、それだけ、早くデッサンをマスターできます。
このままずっと、自分だけで悩んで、デッサンをうまくなろうとしますか?
確かに、いつか答えが、見つかるかもしれません。
しかしそれには、1年かかるか、2年かかるか、もしくは3年、4年でしょうか?
その間に、デッサンのコツをつかんだ人は、合格し、本格的なデザインの勉強をスタートさせます。
そして、あなたより、ひと足早く、一人前のデザイナーとなっていることでしょう。
早く決断し、早く行動した人だけが、早く夢をかなえることができます。
決心されたら、ぜひ、お申し込みください。
.jpg)
今思い返してみると、子供時代から、絵を見たり、描いたりすることは、好きだったように思います。
しかし、決定的に、下手だった、ということも、よく覚えています。
自分自身で、他の人と比べても、上手とは言えませんでした。
そんな私が、デザイナーのなりたい、という夢を持ったのですから、当然、その道のりは険しく、大変だったわけです。
正直、苦労するなぁ、と感じました。
……と思ったのは、最初だけで、しばらく努力を続けると、思った以上に早く、確実に、夢をかなえることができました。
そのきっかけは、やはり、デッサンの勉強と、習得だったと思います。
それを乗り越えることができると、あとは、わりあい、スラスラと進むことができました。
美大へも現役合格できましたし、卒業後の4月から、実際にデザインの仕事につくことができました。
思えば、デザインの勉強をはじめた最初の頃、あきらめずにデッサンを学び続けたからこそ、夢をかなえることができたと思います。
私も、最初は、デッサンについて、難しそう、とか、めんどくさそう、というイメージを持っていました。
しかし、しっかりとした考え方や、テクニックを活用するコツを知ることで、どんどんとデッサン技術が身につき、上達していきました。
やはり、デッサンもちょっとした考え方や視点を持つことで、描写力が上がっていきます。
デザインを学ぶために必要なデッサン力は、しっかりとポイントを押さえて学べば、それほど難しくはないからです。
なぜなら、デッサンは、デザインを学ぶための基礎の一つであり、デッサン力が直接、デザインに影響してくる、というわけではないからです。
そのため、しっかりとポイントを押さえ、デッサンをクリアして、どんどんとデザイナーに必要なデザインの知識と技術を身につけていきましょう。
今、歳を重ねて感じることは、若い時に、デッサンを学んでおいて、本当によかった、ということです。
やはり、デッサンを通じて、観察力や表現力、そして、なにより、作品を丁寧に仕上げる忍耐というものを学びました。
それも、ちょっとしたコツやポイントに気付き、それにもとづき、デッサンをコツコツと勉強した結果です。
あの時、そのポイントに気がつかなかったら、デッサンをマスターするまで、もっと時間がかかっていたでしょうし、最悪、あきらめていたかもしれません。
そのようなことになる人が少しでも減るように、いや、いなくなるようにと思って、今回のデッサンのレポートを書いてみました。
デッサンに悩んでいる、うまくいかなくてあきらめようと思っている、そういう人に、ぜひとも読んでいただきたいと思っています。
他のデッサン技法書では、なかなか伝えることができない内容を、書いています。
なんといっても、絵がヘタクソだった人間が、ちょっとしたコツを学び、デッサンをマスターしたコツをまとめたものです。
なにかしらのヒントを発見できると思います。
あきらめるのは、いつでもできます。
まずは、手に取ってみて下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。